第3回定例会にて、文書質問をしました。
一般質問は2年に1度くらいしか回って来ません。
質問の機会を大切にすべく、任期が始まってすぐでしたが文書にて質問をさせていただきました。
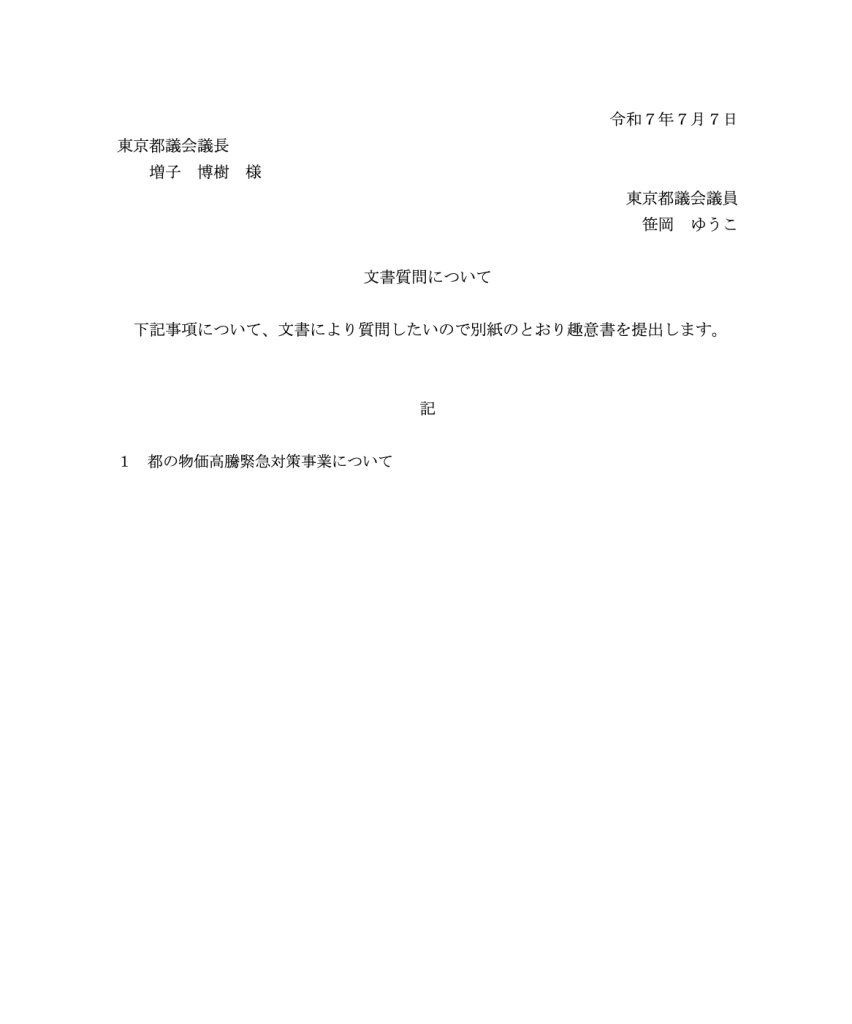
1 都の物価高騰緊急対策事業について
問1:年度末までの支援期間延長について
東京都は、物価高騰の影響を受ける医療機関や福祉施設、運輸、生活関連事業者等を支えるため物価高騰緊急対策事業を実施しており、当初令和7年度9月末までとしていた実施期間を同年12月末まで延長した。
物価高に喘ぐ都民や都内事業者を支援することは評価するが、エネルギーや人件費、物価の高止まりは続いている。特に医療・介護・保育など公共性が高く価格転嫁が困難な分野では年度内の経営改善の見通しが不透明なままである。12月末での打ち切りでは、年度末までの安定的な経営・運営が確保できない状況にある。
とりわけ武蔵野市では地域医療体制の維持が喫緊の課題になっている。
特に吉祥寺南病院が診療休止となり、吉祥寺地域の二次救急医療機関と災害拠点連携病院に空白が生じ、地域医療体制全体に深刻な影響が及んでいる。
このため、市は9月の補正予算において「地域医療確保緊急支援」及び「二次・三次救急医療体制維持・強化」に向けた支援を決定した。
都の補助金も活用するとともに、市独自財源を相当程度投入し、医療・福祉・教育・生活・インフラの各分野において総額4億6千万円超の緊急支援を講じている。
これらの判断は、自治体が限られた財源のもとにおいても、地域医療体制の確保、市内事業者の経営基盤の維持、ならびに市民の暮らしを守るための緊急支援が、極めて喫緊かつ切実に求められているという認識に基づくものだ。
都は物価高騰緊急対策事業を12月末までとした理由を伺う。また、都として少なくとも年度末の3月末までの支援継続を求めるが、見解を伺う。
問2:申請手続きの簡素化・自動継続支援について
物価高騰緊急対策事業の延長に際し、同じ内容の申請を再度行う現場の負担は大きい。すでに支援を受け、事業内容や規模に変更のない対象者は再申請をせずに簡素化し、自動的に支援を継続する仕組みにすべきだと考える。この仕組みは都が推進する行政のDXの方向性とも合致すると考える。見解を伺う。
問3:教育・保育分野への包括的支援について
武蔵野市が今回私立幼稚園も含めて物価高騰対応臨時補助を実施することは、保育と教育の垣根を超えて子供の育ちを支える自治体の姿勢を示している。これは都の「チルドレンファースト」の方針にも整合していると考える。都としても物価高騰の影響を分野横断的に捉え、物価高騰緊急対策事業において保育・教育分野への包括的な支援を展開すべきと考えるが見解を伺う。
以上


