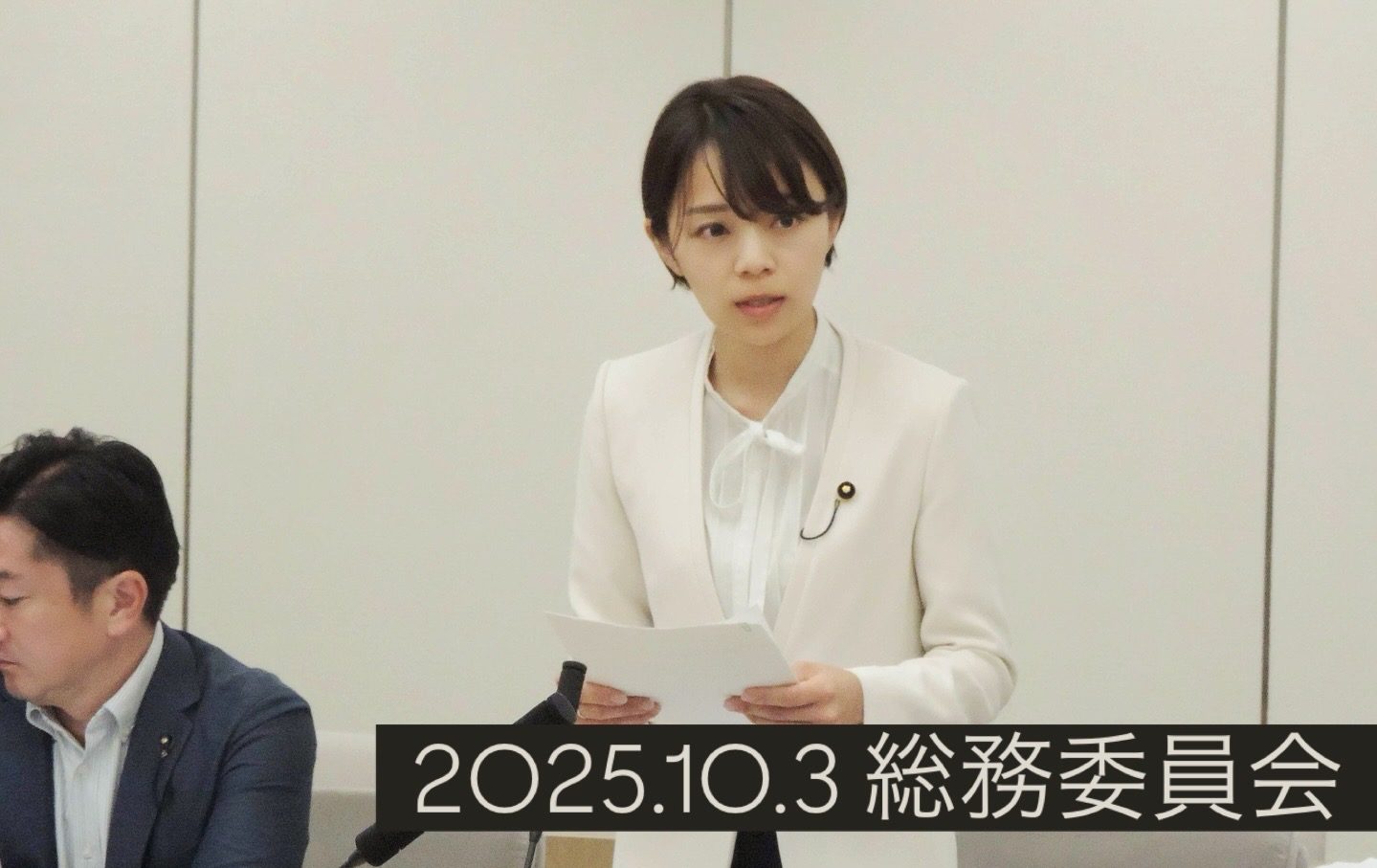チルドレンファースト2025について、行政が出す文書でこんなに頷きながら読むことはまずらしいくらい、頷きながら読みました。とくに新たな3つのリーディングプロジェクトについて高く評価しています。
まず始めに、「多様な「子どもの居場所」創出」について伺います。若者の居場所づくりについては、自治体によって財政状況に差があるため、実際の施策に移す段階で格差が生じやすいのが課題だと考えます。
都の課題認識と、今後の方向を伺います。
自宅以外の居場所は、子どもの幸福度や自己肯定感を高める上で重要な存在だと言われています。
とりわけ、中高生になると地域に安心できる居場所が少なくなる傾向にあります。
このため、子供政策強化の方針2025では、子供のウェルビーイングを高めていくための政策強化の方向として、市区町村等と連携した地域における中高生の日常的な居場所づくりなどを掲げています。

これはぜひ進めていただきたいと思います。武蔵野市で行った、長期計画・調整計画における中高生との意見交換会においても、全てのグループで「まちに中高生の居場所が欲しい」という声がありました。勉強したい、目的なく行きたい、地域の場には入りづらい、どこに行くにもお金がかかる、などです。外は猛暑であることも関係していると思います。
都が市区町村に対して、居場所づくりへの取り組みについて財政的な補助メニューを単独で創設するべきだと考えます。
若者の居場所づくりに取り組む自治体に財政的支援をしていくことで、チルドレンファーストの東京都を実現できると考え、強く要望します。

次に、「思春期の「メンタルヘルス」増進」について伺います。
昨年武蔵野市において痛ましい事案がありました。同じような年齢を持つ親としても、胸が張り裂けそうになりました。
制度は存在しても子どもたちの命を守りきれない現実があります。既存の仕組みを前提としつつ、子どもの命を守る確かな実行に繋げるために、都は取り組みを強化していくべきと考えます。都の課題認識と今後の方向を伺います。
思春期のメンタルヘルスは世界的に深刻な問題です。
東京の子供たちの幸福度は学年が上がるにつれて低下傾向にあり、自殺者数も増加傾向にあることから、思春期のメンタルヘルス対策の重要性が増していると認識しています。
このため、子供政策強化の方針2025では、政策強化の方向として、思春期における心身の健康づくりの推進などを掲げています。

次に、「グローバルな感覚を育む機会の創出」について、伺います。グローバルな感覚を育む視点を掲げ実行していることを評価しますが、実際に利用できるのは限られた人数にとどまり、子どもや保護者に情報が届かずに機会を逃してしまうケースも少なくありません。そして経済格差がそのまま情報格差につながることもあります。
制度はありますが全ての子どもの届かないという溝を埋める工夫が大切です。
広報、多文化交流、デジタルを活用した交流や学習支援など、裾野を広げていく取り組みが必要です。都の課題認識と今後の方向を伺います。
子どもがフローバルな素養を磨くことで可能性を広げ、世界を舞台に活躍できるよう、幼少期も含め、早期から日本や世界の文化に親しみ、豊かな国際感覚を育む機会を創出することが必要です。
このため、子供政策強化の方針2025では、政策強化の方向として、子供の成長・発達段階に応じて、学校内外で国際感覚を育む取組を切れ目なく展開しています。

「とうきょう すくわくプログラム推進事業」について伺います。すくわくプログラムは、幼稚園・保育所といった施設累計の枠を超え、探究活動を通じて幼少期の子どもの育ちを公園する先進的な取組だと考えます。
現場の話を伺ったところ、当初はよくわからず導入に踏み切れなかった園もありましたが、市の研修をきっかけに、取り組みが広がり始めたと聞いています。
今後、広域で実践共有を行う取り組みを進めるにあたっては、都がしっかりと主導していただきたいと思います。
その上で、都としての取り組みの現況と方向性を伺います。
今年度は、幼稚園や保育所等、2,750園での実施を見込んだ予算を計上しています。
プログラムを実施する園では、各園の環境や強みを活かしながら、子供の趣味・関心に応じたテーマを設定し、多様な探究活動を実施しています。
今後プログラム実施園全体の探究活動をリードする、すくわくナビゲーター園制度を創設します。こうした取組により、すくわくプログラムを実施する園を後押しします。

子ども未来アクション2026に向けて、すくわくプログラムの横展開を強化し、支援体制をさらに広げていただきたい。また、補助の継続性を担保し、制度が断続的にならないようにとの、現場からの期待と要望の声がありますのでお伝えします。
次に「ギュッとチャット」について伺います。匿名で子どもが安心して相談でき、心理士等専門員が対応するギュッとチャットについて、注目しています。
匿名性を重視するため、武蔵野市など自治体で行なっている「子どもの権利擁護センター」や地域の相談窓口と十分に連携できないという課題があると考えます。
もちろん匿名性を失えば、子どもが利用をためらう恐れがあり、これは避けなければなりません。匿名性を確保しつつ、必要に応じて自治体との連携の仕組みを工夫することが必要です、
ギュッとチャットの相談件数や主な内容、相談後の支援につなぐ仕組みについて伺います。
ギュッとチャットの運用開始から7ヶ月経過した8月末時点において、3,899件の相談が寄せられており、子供からは、学校生活、心身の健康、家庭環境に関する相談、子育て家庭からは、子育て、家庭環境、心身の健康に関する相談が多い傾向にあります。
ギュッとチャットの運営に当たっては、関係局、市町村等と連携しています。
相談の中で、教育や健康に関する相談など、専門的な対応が必要な場合には、各局や市区町村等が設置している相談窓口や専門機関を紹介するなど、子供や子育て家庭が求めるニーズに適切に対応しています。

ギュッとチャットについて、生成AIの差、というのを考えています。デジタルネイティブの子どもたちは、生成AIの存在も近く、学校の探究授業等でも用いられることもあり、すでに利用している子どもも多くいます。しかしながら、そういった生成AI、ギュッとチャットの差というのは、そこに人がいて、人の判断が入ることだと思っています。
生成AIとの優位性を意識しながら、各局、各市町村との連携をはかていただきたいと要望します。
最後にファミリー・アテンダント事業について、現況と方向性を伺います。
ファミリー・アテンダント事業は、令和6年度に本格展開を開始し、今年9月時点で8区市が取組を実施しています。
都は、市区町村が各地域の特徴を生かし、地域団体、NPO、民間事業者等の多様な担い手と連携した事業を展開できるように後押しをしています。
これまでも補助制度の改善を図るとともに、支援の担い手を対象とした研修などを行なっており、引き続き、地域における支援体制の構築をサポートします。

その上で、現場からは、支援の受け皿となる市民社協など、地域資源にばらつきがあり、ファミリー・アテンダント事業に取り組める自治体に、地域差が出てしまうという声があります。
事業の趣旨には賛同しながら、アウトリーチの方法については多様な主体や手法を一層組み合わせた仕組みへと発展させていただきたいと考えています。
こども未来アクション2026に向けて、一層の取り組みの推進をお願い申し上げて、私からの質疑を終わります。